みなさんは『感覚統合』ということばを見たり聞いたりしたことはありますか?
私は以前、関わっていた子ども達が医療機関で『感覚統合』療法のプログラムに取り組んでいる様子を見学する機会をいただいたことがありました。
・・・が、楽しくプログラムに取り組んでいることはわかっても、子ども達にとって【なぜ必要なのか?】【どんな力がつくのか?】ということを詳しく知ることは残念ながらできませんでした。
今回、あっぷっぷの職員達で【『感覚統合』って何?】【子どもの発達とどんな関係があるの?】という基本的な部分を学ぶ機会があったため、簡単にご紹介したいと思います。
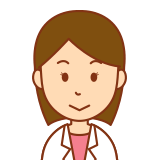
新庄 玉恵 先生
月に1回1時間の『感覚統合』療法のセラピーに通うことができなかったとしても、日常の保育・教育の中で、今その子が必要としている【『感覚統合』理論を活かした遊び】を、1日10分間でも、毎日続けることができれば、子どもは変わります‼
新庄 玉恵 先生:日本感覚統合学会理事。『感覚統合』の考え方を活かした保育・教育活動について、様々な場所で講演や指導をされています。
『感覚統合』は、日々の生活の中で絶えず生じている脳と体の動き。
『感覚統合』にトラブルがあると・・・体のさまざまな感覚(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚・前庭覚・固有受容覚)から受け取る情報をうまく使うことができないために、日常生活の出来事に対して、スムーズにできない状態になる
●『感覚統合』理論の背景にある子どもの捉え方、介入の考え方
共感的理解に基づく支援、子どもの見方、子どもの味方、子ども中心アプローチ
例えば…【A君が教室の中を走り回っている】状況をどう捉える?
★大人の視点で…👩「困ったことばかりして」 👨「どうしたら走らなくなるの」
→ 大人にとっての【当たり前】【当然】【常識】【正常範囲】に当てはめようとすると、子どもは苦しくなる😢
★子どもの視点で…A君は「何で走るのかな?」👧 困り感を想像してみることが大切
→ 👦「面白くない(指導法)」「動いていないと調子が悪い(『感覚統合』)」「注目されたい(社会性)」
→ 理由によって、どんな支援が必要なのかが変わる
A君が走り回ってしまうのは、感覚刺激を求めているからなのね(困り感、楽しさの理由を知る)
→ そりゃ長い時間、じっとしているのは辛いな~(想像:共感的理解)
→ 勉強時間、脳に必要な刺激が入るように工夫してみよう(創造:合理的配慮・発達支援)
→ お!気持ちよく勉強できるぞ~(A君にとって意味のある支援)
●『感覚統合』理論を知ることで…
子どもの行動の理由:神経生理学的な観点で推測する
子どもへの援 助:脳に負担のない援助を考えることができる
子どもに優しくなれる
公園でボール遊びが禁止されていたり、遊具の種類も少なくなっていたり、私たちが子どもだった頃と比べても「危ないから」と禁止されていることが増えていますよね🙅 その分、最近の子ども達は、感覚運動を通した遊びを体験できる機会が減ってしまっています。
日常の遊びの中で、子ども達が感覚運動を通した遊びを体験できるようにすることが大切!
●すべての子ども達・・・【『感覚統合』理論を活かした保育・教育】
障害・特性の有無に関係なく、感覚運動を通した学びは大切
保育園・幼稚園での保育・教育にどのように役立てることができる?
- 感覚運動経験は、障害の有無を問わず、幼児期の発達には大切であることを理解し、日々の遊びなどに活用できる
- 「共感的理解に基づく子どものみかた」を体得し、子どもの行動理解に役立てることができる
- 『感覚統合』療法の視点からの合理的配慮に気づき実施できる(集団だからこそ配慮が大切)
- 不器用な子どもたちへの発達支援としての遊びを考え実施できる
●特性をもつ子ども達(発達障害)・・・【『感覚統合』理論を活用した療育】
行動理解、特性への配慮、療育活動の工夫の際に有用
- 子どもの行動理解
- 感覚の反応性の偏り(感覚過敏や感覚探求など)への配慮
- 感覚運動機能の発達促進のための遊び・活動
●『感覚統合』障害をもつ子ども達・・・【『感覚統合』療法】
詳細なアセスメントに基づく治療的介入。トレーニングを受けた専門家が実施。

これまで「医療機関等に行かなければ、『感覚統合』理論に基づくサポートを受けることができないんだろうなぁ…。」と思っていました。
今回の研修を通して、子ども達が必要としている【感覚統合】の要素は、日々の療育での遊びにも取り入れることができるとわかり、目から鱗でした 👀
あっぷっぷでも、『感覚統合』の要素を取り入れながら、【子ども達にとって楽しい遊び】にたくさん取り組んでいきたいと考えています。
文責:中村 春馨



コメント